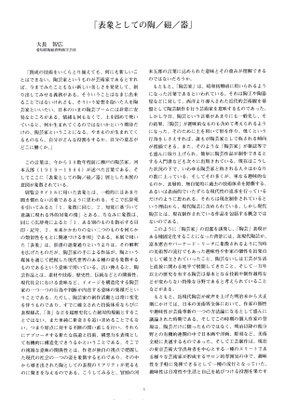「表象としての陶/磁/器」大長智広,多治見市文化工房gallery Voice,展覧会テキスト,2009年
「表象としての陶/磁/器」
大長智広(愛知県陶磁資料館 学芸員)
磁器で制作を行う亀井は、格子構造体を基本形態とする一連の作品で知られる作家である。それは焼成を必要とするやきものにおける技術と構造の関係性や、「やきもの」と「うつわ」の関係性を内部の空間を主役化することで問いかけるという複雑な意味の連関によって成立させている。そして格子構造体は、磁器制作において高温焼成によって磁器化させるための探求の過程が内在している。それは亀井のイメージが焼成を通じたゆがみなどの現象や素材感、偶然性にあるのではなく、歴史や伝統、規範なども含めた陶芸の表現世界の構築にあることを示している。亀井は形状記憶のような性質を有する粘土素材の成形にあたり、素材に直接に触れずに均一な力がかかり、なおかつそのまま構造の基本形態を生み出すことができる鋳込み成形を用いている。加えて、鋳込み成形を単に成形上の手段とするだけでなく、そこに陶磁の量産性をも暗示させることで格子構造体という作品へと還元するのである。同時に磁器化し静謐さをたたえる青白磁の釉薬が「やきもの」という世界における伝統的規範との接点を生みだしている。些細なことのように見えるかもしれないが、伝統と自己をつなぐこうした試みを通じて、陶磁の「うつわ性」が意味を持ち、光と内部空間との有機的関係が構築されるのである。ここには既成の陶磁技術における意味の再解釈を通じて確立した独自の技術体系によって、社会との新たな関係性の構築を試みる陶芸家の意識構造が指摘できる。そして現在、亀井は従来の構造体に面を取り入れることで、より複雑な意味的連関が生み出すイメージの構造化を模索するのである。
<一部抜粋>