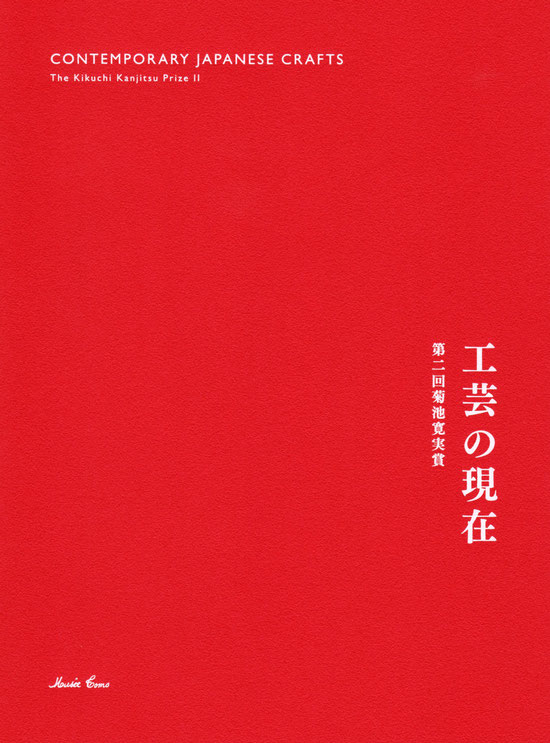第2回菊池寛実賞 工芸の現在 展覧会図録,「作家解説/亀井洋一郎」島崎慶子,2016年
「作家解説/亀井洋一郎」
島崎慶子(菊池寛実記念智美術館 学芸員)
亀井洋一郎は磁土で格子状の線的な造形を制作している。この造形は全体の変形を逆算し、一辺5cmの均一な立方体を調整しながら積み上げていくことで作り出される。土は乾燥や焼成によって変形し、歪みやへたりが生じる性質があるが、均一な個体ならば変形も均一になり、造形全体に変形作用を分散できると考えるのである。そのため各立方体は鋳込み技法で成形されている。石膏型に泥漿を流し込み、型が水分を吸い取って、残った土が型の形になるという方法であるが、言いかえれば、直接手で土に触れることなく成形できる技法である。よって、泥漿の濃度と各辺の厚みを管理することで、均一な立方体を作ることができるのだという。土の特性や技法を再定義し、独自のシステムを構築することで生まれた造形美なのである。
亀井の意識は外形のみならず、集積された内部空間へと向かっている。立方体は中空であるため、壁面を格子状に切り取ると内部に幾何学的な空間が表れる。光を受けて複雑な陰影を表し、部分的に壁を残したり、濃さの異なる釉薬を掛け別けたりといった仕掛けによって、光と陰に対する様々な視覚効果を生じさせる。この内部空間を器の内側と同様にとらえ、亀井はオブジェと器を共存させるアプローチとして「Lattice receptacle」(ラティス レセプタクル/格子構造による受容器の意)シリーズを発表している。